大雨災害の現場から見えた、福祉施設の防災対応
避難が難しい人を支える社会づくりへの提言
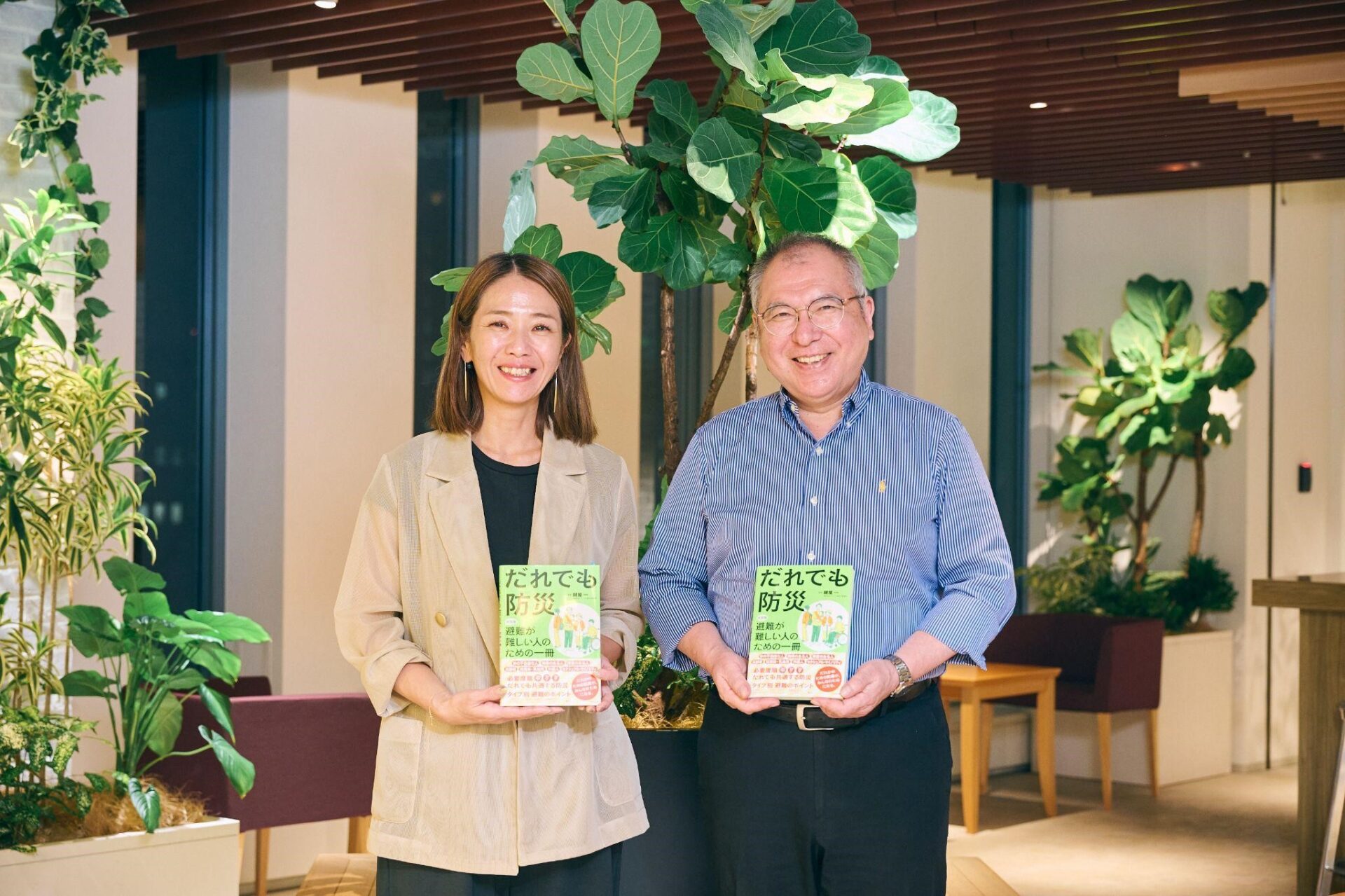
近年、線状降水帯等による集中豪雨が全国各地で頻発し、浸水や土砂災害などの被害が深刻化しています。こうしたなか、福祉施設や行政、ボランティアの現場を支援し、全国で防災・減災の啓発活動を行っているのが一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会です。同協会の代表理事である鍵屋一様は、2025年8月の熊本大雨災害でも現地に入り、福祉施設や行政関係者への支援・調査を実施しました。被災地で見えたのは、想定しきれない浸水リスクや復旧に要する膨大なコスト、そして「人」の備えの重要性でした。
今回のインタビューでは、鍵屋様が大雨災害の現場で得た知見をもとに、人を中心とした防災の在り方と、避難が難しい人を支えるための提言、そして著書『だれでも防災 決定版 避難が難しい人のための一冊』に込めた思いについてお話を伺いました。
目次
熊本の福祉施設が直面した豪雨災害
専門家から見た、夜間避難と体制の課題とは

丸山:近年、日本各地で線状降水帯の発生が相次ぎ、記録的な大雨による被害が増加しています。短時間に集中して降る豪雨による災害について、鍵屋様のご意見をお聞かせください。
鍵屋 様:
河川の氾濫や土砂災害、都市部での浸水被害を引き起こす、線状降水帯の発生頻度が明らかに増えています。しかし実は、年間の雨の総量自体はあまり変わっていないのです。災害を引き起こすほどの大雨、たとえば時間雨量80ミリ、1日300ミリといった規模の降雨の回数は、45年前と比べて約2倍に増えています。こうした極端な降雨の増加こそが、被害の深刻化につながっているのです。
さらに線状降水帯は夜間に発生することが多く、福祉施設のように夜勤の職員が少ない施設では非常に危険です。実際に2020年の熊本豪雨(令和2年7月豪雨)では、千寿園(せんじゅえん)という福祉施設で、入所者14名が亡くなるという痛ましい被害がありました。河川の氾濫発生からわずか数十分で施設が浸水し、施設職員や近隣住民が懸命に入所者を2階に避難させ、56名を助けたのですが、14名が間に合わなかったのです。
この経験から、熊本県の福祉施設は豪雨対策に非常に敏感になっています。災害対策が進む理由の多くは「被災経験」です。自分たちは助かったが、身近で被災した人がいる——その経験が災害への備えを促しています。熊本県はまさに、その教訓を積み重ねてきた地域だと感じます。
丸山:2025年8月に熊本県で発生した大雨災害(令和7年8月熊本県大雨災害)が発生した直後、鍵屋 様をはじめとした福祉防災コミュニティ協会の皆さんが現地に入られたと聞きました。どのようなきっかけで現地を訪れたのでしょうか。
鍵屋 様:
福祉防災コミュニティ協会では、継続的な取り組みとして被災した福祉施設を訪問して支援し、現場の声を今後の活動や提言、研修に活かしています。その一環として、今回の大雨災害でも現地へ支援物資を届けることになり、プラス株式会社ジョインテックスカンパニーさんにご支援いただいた物資などを車に積み込み、3日間にわたり福祉施設や県庁、社会福祉協議会を中心に支援活動を行いました。
訪問先のひとつである県庁では情報交換も行っています。熊本県は毎年のように災害が発生していることから行政の対応が年々洗練されており、現場を支える方々の生の声と貴重なノウハウをお伺いすることができました。
福祉施設の現場で求められる即応力と連携力
人の判断と行動がリスク軽減を左右する

丸山:現地に入られての第一印象をお聞かせください。
鍵屋 様:
全国的にも被害が出た「熊本豪雨(令和2年7月豪雨)」ほどの災害規模ではなかったものの、死者・行方不明者や重傷者などの人的被害が出ていること、実際に1万世帯以上が床上・床下浸水、一部損壊という深刻な状況を受けていることから、想定した以上の被害規模でした。想定外だったのは住民の方々にとっても同様だったようで、さまざまな被害に困っている方が相当数いらっしゃいました。
丸山:度重なる災害で、熊本県は教訓を積み重ねてきた地域とのことでしたが、具体的にどのような点でそのように感じられましたか。
鍵屋 様:
一番は「人の備え」ですね。福祉の現場は、何よりも「人」のサービスなのです。避難を例にあげると、入所者を1階から2階へ避難させるのも、土のうなどの止水措置もすべて職員の人手が重要になります。
熊本県の福祉施設では、今回のように夜間であっても職員が「行かなきゃ」と自主的に判断して集まってくれる意識が根づいていました。中には「大雨が降ってからでは間に合わないだろうから、今日は施設に泊まっておこう」と判断されていた方もいると聞いて、その意識レベルの高さに驚きましたね。
丸山:そうした人員の確保や連携は、どのように実現されているのでしょうか。
鍵屋 様:
日頃から天気予報を確認されていたことと、連絡しあえる体制ですね。災害時はシフトなど関係なく「来られる人はすぐ来てくれ」という判断になります。緊急時の連絡網として電話に加え、LINE WORKSなどのデジタルツールを活用して「今すぐ来てほしい」といった緊急連絡を職員全体に共有している福祉施設もありました。そうした連絡ツールの活用が、現場対応のスピードを支えていました。
丸山:現地の福祉施設で特に喜ばれた支援物資には、どのようなものがありましたか。
鍵屋 様:
基本的に「すべて」ですが、特にマスクは新型コロナやインフルエンザなど感染症対策だけでなく、泥の粉塵対策にも有効です。実際にどの施設からも「マスクはいくらあっても困らない」との感想をいただきました。ただし、浸水被害で活動できるスペースが限られているため、物資の保管スペースに配慮が必要です。
わずかな浸水でも復旧は長期化
泥水被害が突きつけた、リスクマネジメントの盲点とは

丸山:現地に入られた際に感じられた課題についてを教えてください。
鍵屋 様:
大きな課題は、ハザードマップ上では安全とされていた場所でも浸水が発生していたことです。その主な原因は、線状降水帯による豪雨で水の排出が追いつかなかったことにあり、地下駐車場といった高低差がある土地などの、地図では見えにくい要因が被害を広げてしまうことがあります。
実際にとある地域では中庭に水が溜まったことで浸水した施設や、下水が逆流して床上浸水を起こした施設などもありました。普段は景観の良い中庭も、大雨時には水の逃げ場がなくなり、浸水のリスクになる。つまり、「ハザードマップで安全だから安心」とは言い切れず、大雨の際に水が滞留しやすい場所を事前に確認すること、必要に応じて土のうや水のうを設置しておくことが、被害の軽減には必要なのだと学びました。
わずかな浸水であっても泥水が入って床がめくれたり、下水が上がってきたりすれば、修復に多大なコストと時間がかかりますので、施設機能や事業継続に与える影響は大きいと感じました。
丸山:福祉施設における泥水による被害は衛生面でも深刻かと思います。その点はいかがでしたか。
鍵屋 様:
一度でも建物に泥水が入り込むと、たとえ表面を拭き掃除しても床下でカビが発生してしまいます。そのため、排水後は専門業者を入れて高圧洗浄・消毒を行い、1〜3ヶ月ほどかけて徹底的に乾燥する必要があります。その間は通常業務に支障が出ることも多く、ボランティアレベルでは対応しきれません。
こうした処理には当然コストがかかり、福祉施設の場合は事業を止められない事情もあるため、低利融資や一部補助金を活用しながら対応しているケースもあります。それでも持ち出しは多く、経営的負担は大きいですね。
丸山:資金面の備えも福祉施設にとっては重要になるのですね。
鍵屋 様:
災害対策というと備蓄品といった物理的な備えを思い浮かべがちですが、実際には資金の確保が極めて重要です。被害の多くはお金で解決できる部分があるため、日頃から緊急時の資金繰りをどうするかを考えておく必要があります。
特に、風水害の多い地域の施設は、自然災害保険に多めに入っておくことをお勧めします。
丸山:その他に、現地で印象的だった被害はありましたか。
鍵屋 様:
書類関係ですね。介護や福祉の現場では、入居者の個人情報やケア記録などを紙で残しています。しかし浸水被害でそれらの書類が濡れてしまい、乾燥させるために一枚一枚干していた施設もありました。
1週間ほどかけて乾かしたそうですが、完全には元に戻りません。今後は台風や大雨が予想される際に、書類やPCなど濡れては困るものを2階に移すなどの対応が求められます。
行政とボランティアの連携が復旧の鍵に
分散備蓄や地域ネットワークによる新たな防災モデル

丸山:熊本県庁を訪問された際には、どのような意見交換をされたのですか。
鍵屋 様:
熊本県庁は他の自治体と比べても災害対応に慣れていて、支援やボランティアの受け入れにも非常に協力的でした。職員の方々からも元気な声がけがあり、現場の士気を高める雰囲気を感じました。被災経験を重ねてきた地域ならではの成熟度があると思います。
熊本県庁の方々とお話しして改めて課題に感じたのは、日本の制度上、被災後の泥出し作業に公費が投入できない点です。たとえ床下浸水であっても泥出しを伴う復旧作業が必要であり、高齢者や障がい者が暮らす住居であっても、結局はボランティアによる手作業に依存せざるを得ないという構造が固定化しているのです。本来は高圧洗浄を入れて一気に洗い流すべきなのですが、それには業者の対応が必要で、つまり費用が発生します。
家庭用の高圧洗浄機が家庭に常備されているのが理想的ですが、より効果的なモデルは自治体が高圧洗浄機を分散備蓄して集中運用する方法です。地域の各所に2〜3台ずつ配置し、復旧対応時には高圧洗浄機と洗浄剤、ボランティアをセットで一気に投入する仕組みがコスト・時間の両面で有利だと考えています。
丸山:熊社会福祉協議会(社協)やボランティアセンターを訪問された際の所見をお聞かせください。県庁を訪問された際には、どのような意見交換をされたのですか。
鍵屋 様:
八代市のボランティアセンターを訪ねた際は、日曜日で本体機能は閉じていたものの、現場はほぼ休みなしで回っており、指揮・調整を担う職員の疲労は明らかでした。ボランティアなど外部から人手は集まっても、誰に何をしてもらうかの割り振りと安全管理の徹底は地元職員がやらねばならず、不在にはできません。
小さな災害であっても、通常業務である事務処理は必ず発生しますから、記録の作成やPC入力といった外部でも担える事務作業をお願いできるだけでも、現場は大いに助かるはずです。平時から地域で顔の見える関係を構築し、被災していない住民が災害時に自然に駆けつけるネットワークを整えておくことができれば、ボランタリズムが実効性を持つはずです。
「避難が難しい人」に焦点を当てた『だれでも防災』で、
備えを見直すきっかけに

丸山:熊本豪雨のような大規模災害が起きるたびに、避難に支援を必要とする方々が直面する課題が浮き彫りになります。そうした課題意識と、鍵屋 様が現場で培ってきた経験をもとに監修されたのが『だれでも防災 決定版 避難が難しい人のための一冊』です。改めて、本書についてご紹介いただけますでしょうか。
鍵屋 様:
災害時に最も厳しい状況に置かれるのは高齢者や障がいのある方、妊産婦、乳幼児、外国人など日頃から支援を必要とする人々であるにもかかわらず、既存の防災書の多くは台風や地震の定義や一般の方たちに向けた対策がメインで、要支援者への具体策は1〜2ページに留まることが少なくありません。災害時における要支援者のニーズや困りごとは多様であり、形式的な一般論では役に立ちにくいため、「避難が難しい人」という特定のニーズに焦点を当てた一冊を作ろうという発想が出発点でした。
丸山:執筆にあたっての工夫や制作プロセスで重視した点を教えてください。
鍵屋 様:
難しい用語は避け、要点と原則を明快に示しつつ、例外的な対策は思い切って削りました。さらに出版社の協力でイラストを多用し、文字を追わなくても絵からイメージを掴めるよう配慮しています。最終的にブラッシュアップに約1年半をかけて無事に上梓しました。まずは支援者のみなさま、たとえば家族に要介護者や障がいのある方、地域のリーダー、そして行政職員、とりわけ防災担当の若手に読んでほしいと思っています。
丸山:最後に読者へのメッセージをお願いします。
鍵屋 様:
ご自身と身の回りのリスクを見定め、できる備えから始めてください。本書のコンセプトは、「かんぺきな防災より続けられる防災」です。安全な避難先の確認、トイレの備え、家具配置の工夫から始めて、一歩一歩、積み重ねることで徐々に強くなっていきましょう。そして、自ら備える人が多くなれば、本当に支援を必要とする人を支えることができます。それぞれの立場でできる防災対策を実行してください。
〈書籍の購入について〉
『だれでも防災 決定版 避難が難しい人のための一冊』
購入をご希望の方はこちらのサイトをご覧ください。
〈取材にご協力いただいた方〉
鍵屋一(かぎや・はじめ)様
京都大学博士(情報学)。跡見学園女子大学教授、名古屋大学大学院講師、法政大学大学院講師。東京都板橋区で防災課長・板橋福祉事務所長・福祉部長・危機管理担当部長等を務め、2015年4月から現職。内閣府「被災者支援のあり方検討会」座長ほか、多くの防災関連の委員を歴任。一般社団法人「福祉防災コミュニティ協会」代表理事、一般社団法人「マンション防災協会」代表理事など、社会活動や講演活動を積極的に行う。
※インタビュアー:丸山 茜(防災士・災害対策士) 当サイトの運営元であるプラス株式会社ジョインテックスカンパニーにて防災・BCP商材、サービスの企画/推進、「危機対策のキホン」カタログ、オウンドメディアサイト「もっとキキタイマガジン」の企画/監修



