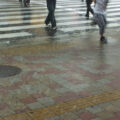非常用電源の浸水対策とは?
災害時でも確実に電力確保するための方法を解説

近年の大規模災害を受け、災害時における電力確保の重要性が広く認識されるようになりました。こうした背景から、多くの企業や施設では災害対策の一環として非常用電源の導入が進められています。しかし、設置するだけで十分と考えるのは危険です。
過去の災害では、電源設備が浸水により使用不能となった事例が報告されており、非常用電源の浸水対策にも十分な対応が求められています。
本記事では、非常用電源の浸水対策の重要性と具体的な対策方法についてわかりやすく解説します。
目次
非常用電源の浸水対策が求められる背景
非常用電源とは、非常時に電力を供給するための設備・機器の総称で、発電機や蓄電池などが含まれます。
非常用電源に浸水対策が求められる背景には、令和元年東日本台風で多摩川沿いのタワーマンションが受けた深刻な被害があります。地下の電気設備が浸水被害にあい、1週間以上の停電・断水が続き、住民生活に甚大な影響を与えました。
この事態を受け、国土交通省と経済産業省が「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を策定し、浸水対策の重要性が明確に示されています。
参考:建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン令和2年6月|国土交通省・経済産業省
現在、非常用電源の浸水対策に法的義務はありません。しかし、病院や福祉施設といった医療施設、高層マンションやオフィスビル、商業施設など多くの人がいる場所では、電力供給の停止が人命に直結するため、対策の重要性は高いといえるでしょう。さらに自然災害の激甚化により、従来想定を超える浸水リスクも増大しています。このような理由から、企業や施設の管理者には社会的責任として、浸水対策を計画的に実施することが強く求められています。
病院や多くの人が集まる場所の災害対策について詳しくは、「多くの人が集まる役所やその他施設における災害リスクと対処法は?」「病院に非常用電源が不可欠な理由とは?災害時に回避できるトラブルも解説」をご覧ください。
非常用電源の浸水対策【計画編】

非常用電源の浸水対策を実施する際は、計画段階から入念に準備することが重要です。
ハザードマップを活用した浸水リスクの把握
非常用電源の浸水対策の第一歩は、施設の浸水リスクを正確に把握することです。国土地理院「ハザードマップポータルサイト」や市町村のハザードマップを活用しながら、自施設のある地域の浸水リスクを調査します。
より詳細な調査には、地形図の活用が効果的です。また、過去の災害履歴を調べることで、ハザードマップに記載されていない局所的な浸水リスクも把握できます。
ハザードマップについて詳しくは、「ハザードマップとは?見方や種類、防災担当者がチェックすべきポイントを解説」をご覧ください。
浸水経路の特定
ハザードマップで把握したリスクを踏まえ、敷地や建物の周囲を歩き、実際にどこから水が侵入するかを調査します。代表的な経路は以下の通りです。
- 建物の出入口(玄関、搬入口、駐車場入口など)
- 地下への階段やスロープ
- 換気口や排水口
- 配管の接続部
- ケーブルが建物を貫通する部分
次に、「水防ライン」を設定します。水防ラインとは、浸水を防ぐために想定される境界線で、建物外周や敷地の境界に設けるものです。このライン上にあるすべての開口部や侵入経路が、対策を講じるべきポイントとなります。
非常用電源の浸水対策【実践編】
計画を踏まえ、実際にどのような設備や方法で対策を行うかを具体的に紹介します。
非常用電源の高所設置
浸水リスクの低い場所に非常用電源を設置することは、浸水対策の基本とされています。具体的には、想定浸水深以上の階層や屋上への移設が効果的です。既存設備については、専用の設備台の導入やラックの高さ調整により、比較的低コストで浸水対策を実施できます。
建築物内への浸水防止
想定した浸水経路においては次の対策を講じることで、建築物内への浸水を防止します。
土のう・水のうの備蓄



建物の出入口に設置することで、浸水被害を抑えられます。防水シートを併用することで、止水効果をさらに高めることが可能です。土のうは、敷地や保管スペースがあれば事前に準備できますが、都市部の施設では難しい場合があります。その場合、保管が容易な水のうの導入も効果的です。
止水板の設置



止水板は、ビルやオフィスの出入口に設置する板状の浸水防止資材です。アルミニウム製やステンレス製が多く、枠にはめ込む形式が一般的です。脱着式・シート式・スライド式など、さまざまなタイプがあります。
防水扉の設置
通常の扉を防水性能のある防水扉に交換することで、浸水を防ぐことができます。防水扉は、建物の出入口だけでなく、非常用電源室の入口に設置するのも有効です。
企業の浸水対策については、「企業の水害・浸水対策とは?求められる理由や具体的な方法を解説」でも詳しく解説しています。
浸水対策の実効性を高めるためのポイント
浸水対策の効果を維持・向上させるため、次のポイントを押さえた取り組みが重要です。
BCP・マニュアルへの反映
浸水対策は、事業継続計画(BCP)に明確に組み込む必要があります。災害発生時の対応手順、関係者の役割分担、復旧の優先順位などを事前に決定し、定期的な訓練を実施することが不可欠です。また、浸水リスクの変化に応じてBCPを見直し、対策を更新し続けることで、実効性のある災害対応が可能となります。
また、BCPだけでなく、実際に浸水が迫った際の対応手順をまとめた運用マニュアルの整備も求められます。土のうや止水板の設置手順、担当者や連絡体制などを明確にし、災害時に迅速に行動できるよう準備しておきましょう。
BCP・マニュアルについて詳しくは、「BCP対策とは?基礎知識から策定手順、運用のポイントまでわかりやすく解説」「防災マニュアルの作成方法とは?BCPとの違いや押さえるべきポイントも解説」をご覧ください。
複数台の非常用電源の確保
浸水対策を実施しても、想定を超える災害により非常用電源が使用不能になるリスクがあります。このため、非常用電源は1台だけでなく、複数台を確保することが重要です。
また、さまざまなタイプの電源を組み合わせることも、電力確保の確実性を高めるうえで有効です。
発電機や蓄電池には複数の種類があり、それぞれ特性や設置条件が異なるため、用途や環境に応じた使い分けが重要です。また、電気自動車からの給電も、有効な選択肢のひとつとなります。
非常用電源の種類について詳しくは、「発電機と蓄電池の違いは?特徴、非常用電源としてどちらを選ぶべきかを解説」をご覧ください。
確実な電源確保には単一の対策に頼らないことが重要

非常用電源の浸水対策は、ハザードマップを活用したリスク把握から始まり、浸水経路の特定、具体的な対策の実施へと段階的に進めることで、より高い効果が期待できます。
重要なのは、単一の対策に頼らず、複数の対策を組み合わせることです。特に想定外の災害に備えるためには、複数の非常用電源を併用し、強固な電力供給体制を整えることが欠かせません。
ジョインテックスカンパニーでは、発電機や蓄電池などの非常用電源、浸水対策用品をはじめ、防災備蓄品を中心に約1,500アイテム掲載の危機対策のキホンカタログの発刊及び、各種防災用品の取り扱い、全国で50名を超える防災士による事業所の対策状況に応じたご提案を行っております。
プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。
キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。