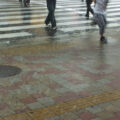ゲリラ豪雨に備え企業が行うべき対策とは?被害を最小限に抑える方法を解説

予測が困難な局地的大雨「ゲリラ豪雨」の発生頻度が、年々増加しています。ゲリラ豪雨に代表される突発的な豪雨は、企業活動に深刻な影響を与え、施設の浸水被害だけでなく、従業員の安全や事業継続にも関わる重大なリスクとなっています。本記事では、企業がゲリラ豪雨に備えるための対策を解説します。
目次
ゲリラ豪雨とは
ゲリラ豪雨とは、局地的かつ突発的に発生する短時間の激しい雨を指します。急速に発達した積乱雲によってもたらされ、狭い範囲に集中して降るという特徴があり、特に夏場に発生します。
ゲリラ豪雨は、地上付近の暖かく湿った空気が急激に上昇し、短時間で発達した積乱雲を形成することで発生します。都市部では、コンクリートやアスファルトで覆われた地表面が太陽光で温められ、上昇気流が生まれる「ヒートアイランド現象」が発生しやすく、郊外に比べゲリラ豪雨の発生頻度が高くなっています。
ゲリラ豪雨について詳しくは、「ゲリラ豪雨とは?発生のしくみや想定される被害、企業が行うべき備えを解説」をご覧ください。
企業がゲリラ豪雨対策に取り組む重要性
ゲリラ豪雨の特徴のひとつに、予測の難しさがあります。通常の前線性の雨や台風とは異なり、数時間前から正確な予測をすることが困難で、気象レーダーで観測できたときには既に発達した状態にあることが少なくありません。
この予測困難性こそが、企業にとって計画的な対応を難しくし、突発的な事業中断リスクを高める要因となっています。
ゲリラ豪雨が企業活動に与える影響

ゲリラ豪雨が企業活動に与える影響は、次の通りです。
建物・設備などの物理的な被害
ゲリラ豪雨は次のような物理的な被害をもたらし、企業の資産に直接的なダメージを与えます。
- 建物の浸水被害:
地下階や1階部分の浸水は、内装や設備に深刻な損害をもたらします。浸水深が50cm以上になると、ドアが水圧で開かなくなり、避難も困難になります。
- 電気設備の損傷
変電設備や配電盤が浸水すると、漏電や火災のリスクが高まるだけでなく、修理・交換が必要となり復旧までに長期間を要することがあります。
- IT機器やデータの損失
サーバールームへの浸水は、データ喪失という回復が困難な事態につながる可能性があります。電子データだけでなく、紙の重要書類・資料の損傷も起こりえます。一度失われたデータの復旧は困難で、業務再開の大きな障壁となるでしょう。
- 在庫・備品の被害
倉庫や保管場所の浸水は、商品や資材の直接的な損害となります。金銭的損失だけでなく、顧客や仕入先との信頼関係を損なうおそれがあります。
従業員の安全への影響
ゲリラ豪雨は、従業員の安全にも深刻な影響を与えます。
- 通勤途上での被災
突然の豪雨により、従業員が通勤中に危険な状況に遭遇するリスクがあります。特に、アンダーパスや地下通路では、短時間で水位が上昇し、命の危険に直結することもあります。
- 事業所内での孤立
周辺地域の浸水により、帰宅困難者が発生し、従業員が社内に長時間とどまらざるを得ない状況が生じる可能性があります。
事業への影響
企業の事業継続にも、次のような直接的な影響を与えます。
- 操業停止
施設の浸水や電力供給の停止により、製造ラインや業務システムが完全に機能を失うことがあります。復旧には時間とコストがかかり、その間の機会損失も発生します。
- 物流の麻痺
交通インフラの麻痺により、原材料の入荷や製品の出荷が滞り、サプライチェーン全体に影響が波及します。納期遅延が発生し、顧客との取引関係の悪化や違約金の発生などの二次的な損失につながることもあります。
企業が実施すべきゲリラ豪雨対策
ゲリラ豪雨を予測することは困難ですが、事前に適切な対策を取ることによって、被害を軽減できます。ここでは、企業が取り組むべき対策について解説します。
ハザードマップによる水害危険度の把握
まずは、ハザードマップを使って自社施設の水害・浸水リスクを正確に把握しましょう。国土地理院「ハザードマップポータルサイト」や自治体が公開するハザードマップを活用し、事業所の浸水想定深や過去の水害履歴を確認します。特に地下施設や1階部分のリスク評価は重要です。この評価に基づき、具体的な対策を検討することができます。
ハザードマップとその活用方法については、「ハザードマップとは?見方や種類、防災担当者がチェックすべきポイントを解説」「【企業の防災対策】ハザードマップの具体的な活用方法は?その注意点も解説」にて詳しく解説しています。
建物・設備の浸水対策
建物や設備を水から守るためには、以下の対策が効果的です。
- 止水板・防水扉の設置



出入口や窓などの開口部に設置し、水の侵入を防ぎます。常設型と簡易型があり、予算や必要性に応じて選択できます。特に、地下への入り口や低地にある開口部には、積極的に設置を検討しましょう。
- 排水設備の強化

排水ポンプの設置や排水溝の定期的な清掃・点検により、敷地内の排水能力を高めます。雨季前には、落ち葉や土砂による詰まりがないか入念に確認しましょう。
- 重要機器・設備の垂直避難やかさ上げ
サーバーやコンピューター、電気設備などの重要機器は、想定浸水深より高い位置に移動させるか、専用の台を使ってかさ上げすることで浸水被害を防ぎましょう。
- 防水壁・土のう・水のうの準備:



簡易的な対策として、土のうや水のう、防水シートなどを準備しましょう。緊急時にすぐ使用できるよう保管場所と使用方法を従業員に周知しておきます。定期的な使用訓練も効果的です。
重要データ・システムの保護
サーバーやデータストレージは浸水に弱く、一度データが消失すると事業復旧の大きな障害となります。重要システム機器の垂直避難だけでなく、下記の方法を検討するといいでしょう。
- クラウドへのバックアップ
重要なデータを定期的にクラウド上にバックアップしておくことにより、物理的な被害からデータを守ることができます。バックアップのスケジュールと範囲を明確にし、定期的に復旧テストを行うことも重要です。
- 重要サーバーの分散配置
すべての重要システムを一箇所に集中させず、地理的に分散させることでリスクを分散します。クラウドサービスの活用も有効な選択肢のひとつです。
- 無停電電源装置(UPS)の設置

突然の停電に備え、重要システムには無停電電源装置(UPS)を設置し、正常なシャットダウンや一定時間の運用継続を可能にします。
データは一度失われると復旧が困難なケースも多いため、二重三重の対策が望ましいでしょう。
事業継続計画(BCP)への組み込み
ゲリラ豪雨対策を企業の事業継続計画に明確に位置づけることが重要です。ゲリラ豪雨の特性を考慮し、迅速な初動対応と従業員の安全確保の視点を盛り込むことが必要となります。例えば、豪雨による停電や従業員の帰宅困難を想定し、非常用電源(蓄電池・発電機)や食料・飲料水などの備蓄品の計画も欠かせないでしょう。 計画は定期的な訓練を通じて実効性を高め、PDCAサイクルによる継続的な改善を心がけましょう。
BCPや備蓄品については、下記の記事にて詳しく解説しています。
企業が蓄電池を導入するメリットとは?災害時以外の活用方法も紹介
従業員への教育
ゲリラ豪雨は予測が困難で突発的に発生するため、従業員一人ひとりの判断力と対応力が求められます。移動中や通勤、地下施設にいる場合など危険性が高い場面でも、従業員が適切な行動ができるよう、ゲリラ豪雨特有の危険シナリオに対応できる知識を共有しましょう。定期的な研修や避難訓練を通じて、「自分の身は自分で守る」意識を醸成することが重要です。
水害・浸水対策、BCPについては、下記にて詳しく解説しています。
企業の水害・浸水対策とは?求められる理由や具体的な方法を解説
工場・倉庫を浸水から守る対策7選!日頃からできる水害への備えを解説
効果的なゲリラ豪雨対策で企業の事業継続力を高めよう

近年増加傾向にあるゲリラ豪雨は、その予測困難性から企業活動に深刻な打撃を与える可能性があります。ゲリラ豪雨による被害を最小限に抑えるためには、建物・設備の浸水対策や情報システムの保護といったハード面の対策だけでなく、BCPへの組み込みや従業員への教育などソフト面の対策も欠かせません。特に、突発的な豪雨に対しては、一人ひとりが適切な判断と行動ができるよう、日頃からの教育と訓練が重要です。適切な備えがあれば、その影響を大幅に軽減し、企業の事業継続力を高めることができるでしょう。
ジョインテックスカンパニーでは、水害対策用品をはじめとする約1,500アイテム掲載の危機対策のキホンカタログの発刊及び、各種防災用品の取り扱い、全国で50名を超える防災士による事業所の対策状況に応じたご提案を行っております。
前回の記事ではゲリラ豪雨について解説しています。ゲリラ豪雨について、より深く知りたい方はこちらをご覧ください。
ゲリラ豪雨発生による水害発生時に自身の身を守るための避難方法として、垂直避難があります。水平避難との違いについても解説していますので、ぜひ、ご一読ください。
コンテンツの更新情報を受け取りたい方は以下より、メルマガ登録いただくことで、より確実に更新情報を受け取ることができます。
プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。
キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。